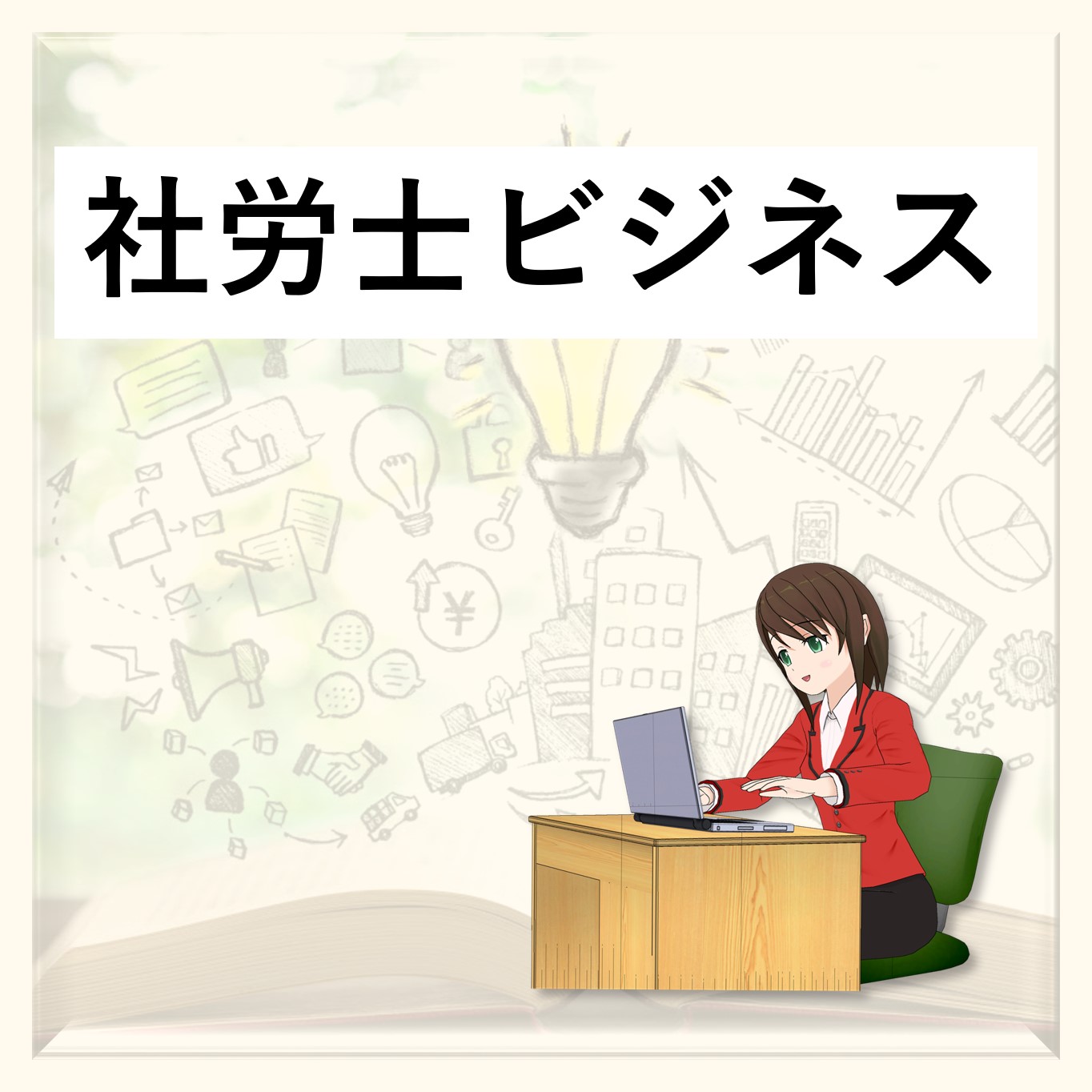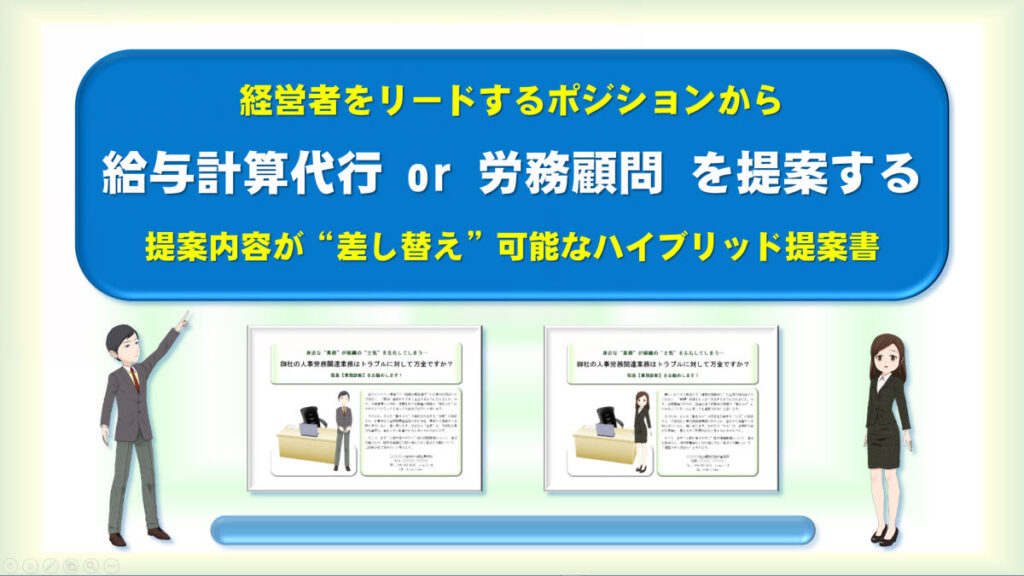社会保険労務士事務所も《営業》をしなければ、関与先を獲得できません。しかし『これ以上、忙しくしたくない』し、営業活動に意欲を持てないとしたら、今《どんな視点》に立つべきなのでしょうか。
少し角度を変えて《営業活動》を捉え直してみました。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.営業活動で事務所業務が更に進化?
たとえば、給与計算代行サービスを推進している事務所では、《相談受付》等もっての他かも知れません。そもそも《そんな時間》を、なかなか作れないでしょう。
ところがその事務所が、それぞれの《代行先》に、段階的な《給与規程の見直し》を提案するとしたら、どうでしょう。提案先を新たに探す必要はありませんし、数社を相手にした時でも、提案書やプレゼントークは《1つ》で済みそうです。しかも、その提案が成約しない場合でも、既存の給与算代行業務への《満足度調査》や経営陣への《意識刺激》ができそうなのです。
2.企業経営者と実践的課題を共有する
そのため、まずは給与計算代行契約を受注して、その後に給与規程や就業規則の見直し提案に繋げる取り組みは、従来から行われていますが、最近では更に一歩進んで、『組織人事関連の諸規程に留まらず、生産性向上や新人の早期戦力化を狙った業務マニュアル等の《広義の社内規程》作成を支援しよう』という動きも出始めています。
あるいは、経営者に《ハラスメント》等の社内セミナーを依頼された際、《労務顧問》契約を提案して《相談》を受け、その内容をまた《新たなセミナー》に組み上げて、《相談+研修》による事業展開を目指そうとする動きもあります。今後のビジネス展開を大きく構えるのではなく、ピンポイントから先行きの《効率的発展》を狙うわけです。
3.事務所の《特徴》を打ち出しやすい
こうしたピンポイント作戦、あるいは《計画的段階的な社会保険労務士事務所ビジネス展開》には、4つのメリットを期待できそうなのです。その1つは、《①事務所の特徴を出しやすい》ことです。逆に今『人事労務テーマなら、何でもお任せください』という類の万能型のアプローチでは、なかなか経営者のハートに届きにくいのです。
これまで、昨今のようには、《人事労務課題》を身近に感じる経験が乏しかった中堅中小企業の経営者には、そもそも『何を任せるべきか』を、具体的には考えにくいからです。経営者の選択を待つのは、時間の浪費かも知れません。
つまり社会保険労務士事務所サイドで《旗色を鮮明》にした方が、経営者側でも選択がしやすいということです。
3.専門性は《実践》の中でこそ深まる
第2のメリットは、事務所ビジネスの流れに《方向性》を持たせると、日々の活動がそのまま《生きた勉強》になるため、《②専門性を実践的に深めやすくなる》ということです。
企業が抱える問題は千差万別であるため、『教科書的な学習よりも《実地見聞》の方が、はるかにパワーになる』と言う先生もおられます。しかもその専門性は、たとえば《安全衛生》という比較的身近なテーマでも、『想像以上に奥が深くて、すべきことがたくさんある』のだそうです。
4.提案活動で自事務所の生産性が向上
第3のメリットは、経営支援に《方向性》が出来ると、同じような資料やデータを繰り返し使えるし、自信を持って提言できるため、《③営業のみならず支援業務の生産性も上がる》ということです。
むしろ、従来『依頼を受けてから動いていたため、毎回新しい業務を行うことになり、その結果として《忙しくなり過ぎていた》のではないか』という見解も出ているのです。
過剰な《忙しさ》を克服するには、極論すれば《同様のサービスを複数の企業に提案する》こと以上の方法はないとさえ言えそうだということです。
5.しかし《提案活動》は大変になる?
ただ、そんなに都合よく《提案》ができるのでしょうか。
ある先生は、『あまり深く考えず、どんな経営者にも話を持ち掛けられる《普遍的な案件》で提案活動を開始する』と、予想を超えた成果が得られると言われます。普遍的な案件とは、たとえば、給与計算代行や労務顧問のような提案です。
普遍的であるが故に、その提案が成約してもしなくても、《賃金に関わるテーマ》と《社内問題や経営者の悩みに関わるテーマ》で、『経営者と、人事労務の根幹にある非常に具体的な課題に踏み込んだ話ができる』のです。
6.踏み込んだ話をする機会があれば…
そして、そんな《根幹に踏み込んだ話》の中で、一気に顧問契約をベースにした経営支援やコンサルティングに入ろうとせず、たとえば《役員会での勉強会》や《管理者研修》を落としどころにして話を進めると、『だんだん、経営者が《して欲しいこと》が明確になって行くケースが増え始めます。
経営者の組織マネジメント上でのニーズが、経営者自身にも明確になって行くと、勉強会や社内セミナーに至らない時でも、《④テーマに沿った具体的な相談が持ちかけられる》ようになるのです。たとえば、『高齢で役職を退いた後の管理者の動機付けをどうしようか』という相談を受けると言うことです。これが4つ目のメリットです。
7.4つのメリットと残された問題
つまり、方向性を定めた事務所ビジネス展開に取り組むと、《①事務所の特徴が鮮明化》してアピールが容易になり、その分野での《②専門見識や問題対処ノウハウが実践化》し、更に《③資料やデータの使い回しや自信強化で生産性が向上》して、関係が深まった後では《④依頼される内容も明確化》するわけです。
しかし、問題も残ります。
8.事務所都合での提案は歓迎されない
その問題とは、社会保険労務士事務所が自事務所の都合で提案していると思われると、一種の《セールス》のようになり、経営者ならまだしも、総務担当者にまで《警戒》されやすくなるということです。やはり、企業サイドが悩みを発信し、それに《応える》形の関係性が、専門ビジネスには似合うのかも知れません。
ところが、ある先生は『だからこそ、まず経営者が《悩むべきことを自ら発見して特定できる》ように、給与と社内問題を呼び水にした《語り合い的提案》の機会が大事になる』と言われるのです。
9.実質的には《出張相談》サービス?
人事労務課題は企業の事情や体質で千差万別化する傾向があります。その結果、考え抜かれた提案でも『そんな一般論が、うちで役立つのか?』というイメージを経営陣に与えてしまう恐れがあるのです。経営者が《なかなか相談する気になれない》のは、専門ノウハウが自社経営に《どう役立つのか分からない》からかも知れません。
そのため、経営者がイメージしやすいテーマで提案を行いながら、経営者との共通理解を創り出す機会を持つことには、大きな意義がありそうなのです。
上記の先生は『これは提案と言うより、《経営者の労務課題への取り組み意欲引き出しのための出張サービス》とでも言うべきだろう』と指摘しながら、『人事労務課題が急速に深刻化する中では、自事務所にサポートできる案件を探しながら《4つのメリット》を活かすために、出張相談サービス発想での提案活動が、益々重要になりそうだ』と考えておられるのです。