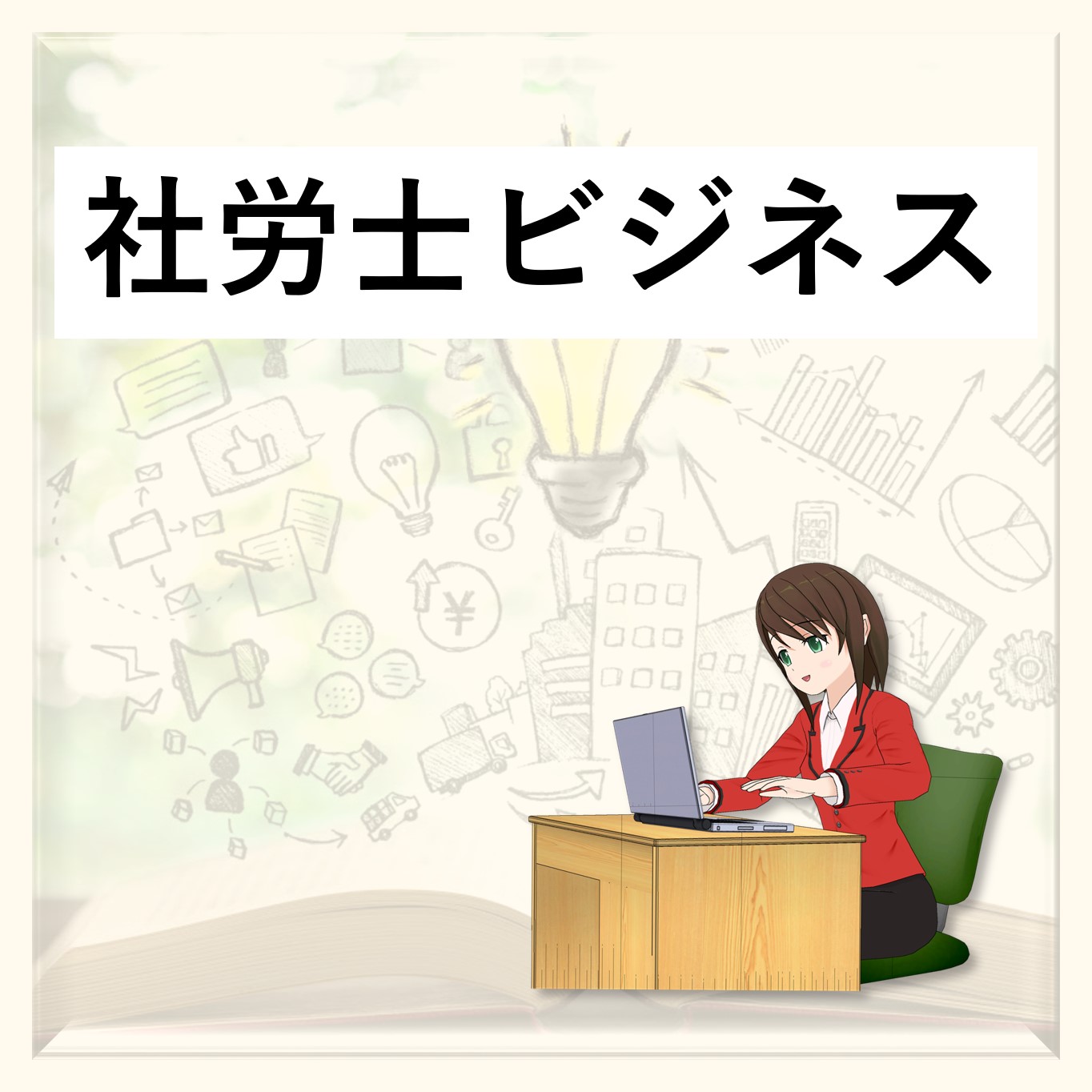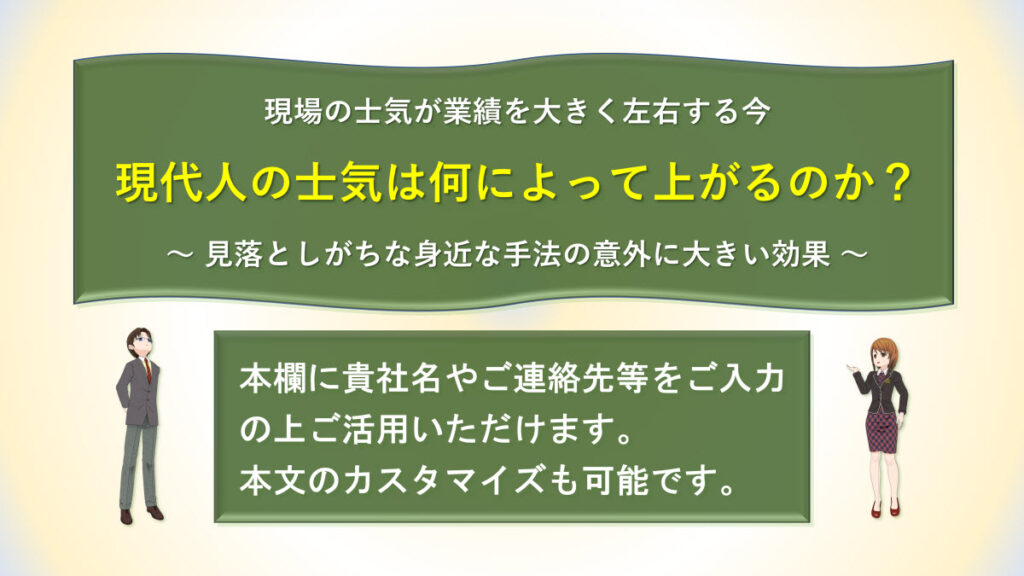《代理戦争》という言葉があります。それは、たとえば核兵器を持つ大国間に《深刻な問題》が発生した際、それが大国間同士の戦争に発展しないよう、結果として、他の中小国や集団が身代わりになる戦争です。
ところが『そんな代理戦争の報道を聞いていると、むしろ《経営問題》が見えて来る』という経営者がおられるのです。そこには、どんな経営問題が《見えて来る》のでしょうか。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.代理者と支援者がそれぞれ持つ感情
代理戦争は、大国Aと大国Bの間に問題が発生したような場合に、大国Aの支援を受けながら代わりに戦う中小勢力の代理国Cと大国Bの間で始まるのが普通です。そして表面的には、代理国Cにも《自国の勢力や存在を守る(あるいは拡大する)》メリットがあるはずなのです。その結果、代理国は支援大国Aの恩恵の下で戦争をしている形になります。そんな中では、代理国が支援大国Aに《謝意》を示すのは、ごく普通の成り行きでしょう。謝意のみならず、自国の安全保障のために、その支援大国の傘下に入ることを望むかも知れません。
そうした状況を捉えるなら、たとえば、最近の報道のように『アメリカ大統領がウクライナ大統領に《支援に対する謝意がない》という不快感を示した』としても、大国にとって、それは自然な感情だとは言えそうです。
2.代理国の感覚が以前とは変わった?
その一方で、代理戦争を任される中小国は、大国間の主導権争いに巻き込まれて、自国が犠牲になることに強い不快感を抱くでしょう。しかも《人の生命》と《国家利益》の天秤が以前とは異なる揺れ方をする今日では、中小国が『犠牲になっているのは自国なのだから、勢力争いをしている大国はもっと、我が国を支援すべきだ』と感じても、それもまた自然かも知れないのです。そんな《感情》は、時として反抗的な姿勢に繋がることがあります。
ただ、こうした《意識変化》は、ビジネスの世界では国際紛争より、もっと露骨に出始めているようなのです。そんな変化がA社の社長に見えたのです。
3.ビジネスにどう類似しているか
中堅中小企業の会社の事業は、そもそも会社に帰属します。そして意思決定権は、オーナーでもある経営トップにあります。業務現場は、長であれ担当者であれ、極論すれば《会社という法人の代理人的》に働いているわけです。
たとえばかつて、電話で『もしもし、〇〇社の△△ですが…』と個人名ではなく、『〇〇社ですが…』と社名しか名乗らない人が多かったのは、そんな『私は個人としてではなく、会社業務を引き受けている一代理人として電話している』という意識が当たり前だったからとも言えそうなのです。
ところが最近では、A社でも『この契約をとったのは私だ』とか『このソフトを開発したのは私(であって会社ではない)』等という担当者の姿勢を、『言動の端々に感じ始めた』と社長は指摘されるのです。
4.傲慢な担当者の方が貢献度が高い?
そうした自己主張は《働かせてもらっている会社や社長への感謝》に進むのではなく、逆に、会社に対して《利益をもたらしている自分への感謝要求》に繋がります。ところがA社の社長は、『それは困る』と言うのではなく、『以前なら《傲慢》とも見られた担当者の方が、今や、実際には仕事がよくできる』ことの方を強く指摘されるのです。
しかも、その《傲慢人?》が契約先で《自在に取引内容の細部を自社に有利に詰めて来る》ことに、『ある種の畏敬の念を抱く』とも言われます。更に、そんな《役立つ人》は、会社の仕事を請け負う《代理人》ではなく、範囲が限られてはいても、その分野では会社(の事業)を《代表》しているかのようにさえ感じる時があるそうです。
5.貢献度の底流にあるのは深い理解!
もちろんその《代表意識》の背景には、契約方針やサービス内容あるいは《業務の完成形》については勿論のこと、事業の内実や利益に対する深い理解が求められます。むしろ『個々の業務の細部では、私よりも担当者の理解の方が深い』と、社長は真剣な表情を見せます。業務内容の話になると『口を挟めない部分さえ出る』からだそうです。
そんな状況を捉えて、社長は『役に立つ人材を、今後どうマネージして行けば良いのか』と悩まれます。しかも、その悩みの先には、『マネージの方法や方向性さえイメージできれば、《役立つ人》を、もっと採用しやすくなるし、既存の人材の育成方針も明確になる』という《人材活用の展望のようなものも見える》ようなのです。
6.代理より代表意識の方が役立つ事情
そんな期待の背後には、社長に会社の事業や顧客あるいは競合先等の《全容》は把握できても、個別業務の個別事情までは読み切れない程、あらゆるものが複雑かつスピーディーになったという現実があるようです。今や、社長の指示に忠実に従い、細かい指導を仰ぐ《代理人的人材》より、一定の範囲内で自主的に活動できる《特定業務の代表者的人材》のほうが、目まぐるしい状況変化をタイムリーに乗り越えやすいのかも知れません。
そのため社長は『自主性と指示(経営の意図)への忠誠を両立させる何かが不可欠だ』と、考え始めるようになりました。それはもはや、《アメとムチ》のような発想では実現できないものだからです。
7.それこそ《ルール経営》の入り口!
いずれにしましても、このA社の社長が行き着いたのは、まさに《ルール経営》と呼ばれるものの《入口》でしょう。社内のメンバーが、いつでも経営陣にお伺いを立て、その指示に従うとしたら、ルール経営は必要ありません。社長が王様のような存在だとしたら、届け出以外では、就業規則さえも意識しなくても良いかも知れません。
しかし、進歩なのか新たな問題なのかは別として、急速に《変化》する諸事情の中では、経営陣が《タイミングよく次々に指示を出す》ことは、想像以上に容易ではなくなって来ているのです。
そのため『一定の範囲(ルール)内で、あたかも自分自身が《会社を代表》しているかのように、事業にもたらす成果を考えて行動して欲しい』と経営トップが感じるのも、今日では、これもまた自然なことなのでしょう。
8.理屈だけではなく経験蓄積が不可欠
ただし、《ルール経営》という理念だけで《先走る》のではなく、A社の社長自身も《現実的なルール》に慣れなければならないでしょう。少なくとも『ルールは従業員に守らせる規則』なのではなく、『社長自身も順守するもの』だという意識から、その実践体験を蓄積しなければなりません。
たとえばハラスメント防止は、そんな意識化と体験蓄積の好機になり得ますが、その遵守は経営者にとっても案外難しいものでしょう。そのため、急いで高度なルールを取り入れようとはせず、身近で分かりやすく、更には守りやすい部分から《ルール体験》を始めることが肝要になるのです。
9.経営の基本原則は《隗より始めよ》
『身近な分野だけでは間に合わない』と言われるかも知れませんが、危機意識ばかりが先行して、ただ右往左往し、結局何も変えられずにいる経営者は、こう言ってよければ本当に少なくありません。取り組みやすい分野から取り掛かるという回り道は、ルールが持つ機能と効果と特性の習熟に際する《近道》になり得るとさえ捉えられるのです。自意識の高い現代人をマネージするに際しては、たとえば『書類の保管や廃棄に関わるルール』のようなものでさえ皆を動かしやすくすると、経営者に実感させ得るものです。
本格的なルール経営に取り組み始めるのは、そんな実感を持ってからでも構わないでしょう。まずは『隗より始めよ(かいよりはじめよ:大事を成すには小事から始めよ)』という教訓と、取り組み後の方向性を経営者と共有できるなら、社会保険労務士事務所が持つ《社内規程》ノウハウが輝き出す瞬間に遭遇しやすくなるはずです。
まずは『ルールで組織を動かす練習』が、ルールの働きや公平さのイメージを社内に浸透させるからです。
10.小事でのイメージ形成から開始
国際法や条約はあっても、その違反を取り締まる実質的な機関がない世界情勢とは違い、法律に反さない限り、自由に社内ルールを定め、それを経営陣が実態に即して運営できる会社組織では、ルールの実効性は比べ物にならないほど大きくなるはずです。
事細かく指導して管理する経営方式が、なかなか世の中のスピードに追い付けなくなった今日、たとえA社のように従業員意識が変わっていないケースでも、《ルール経営》は企業にとって今後益々重要になると考えられます。しかも既に申し上げた通り、一気に理想形に飛ばず、《隗より始める》重要性と意味を先生方が《語り始める》なら、そこには企業と社会保険労務士事務所双方に、それぞれのビジネスチャンスへの展望が開け始めると期待できるのです。