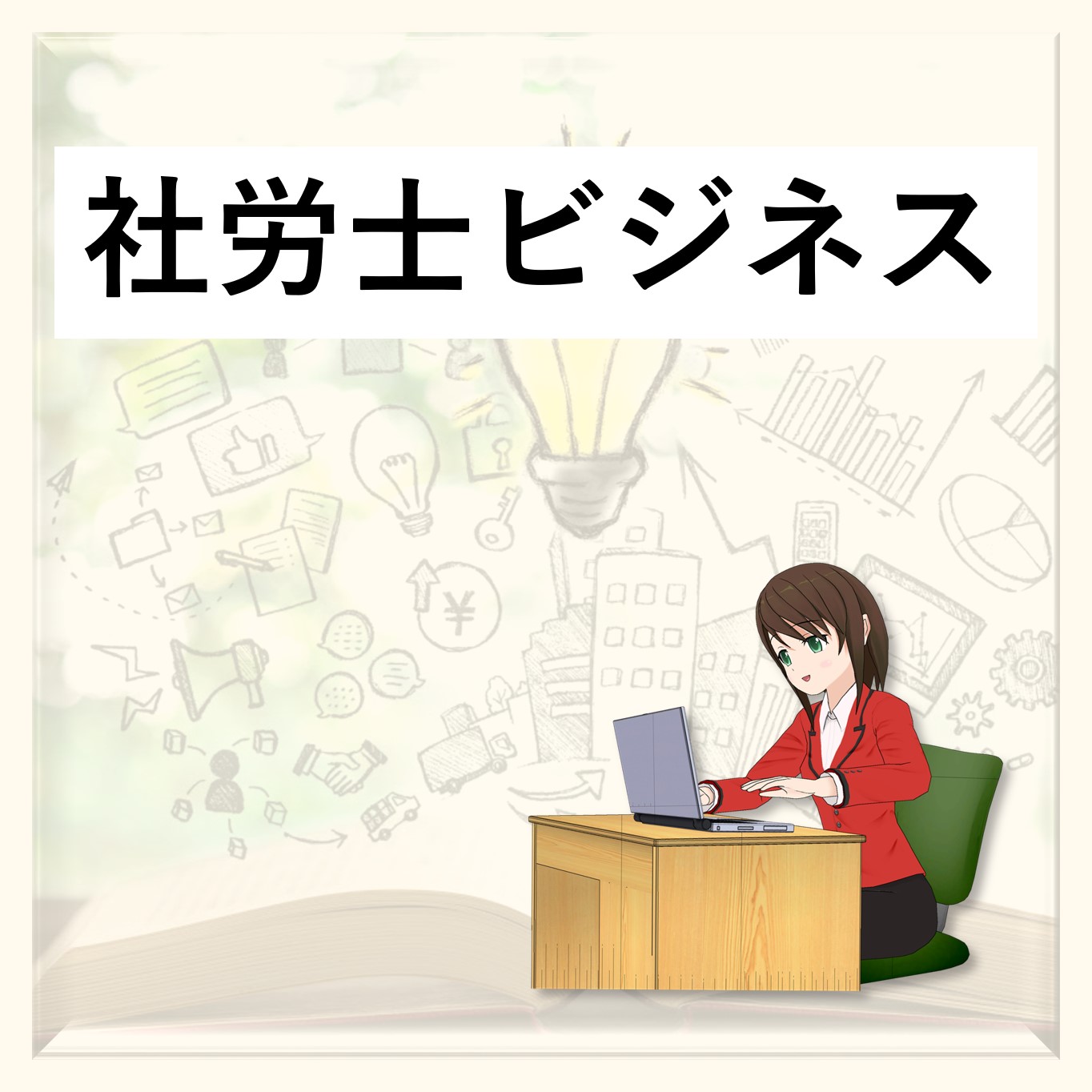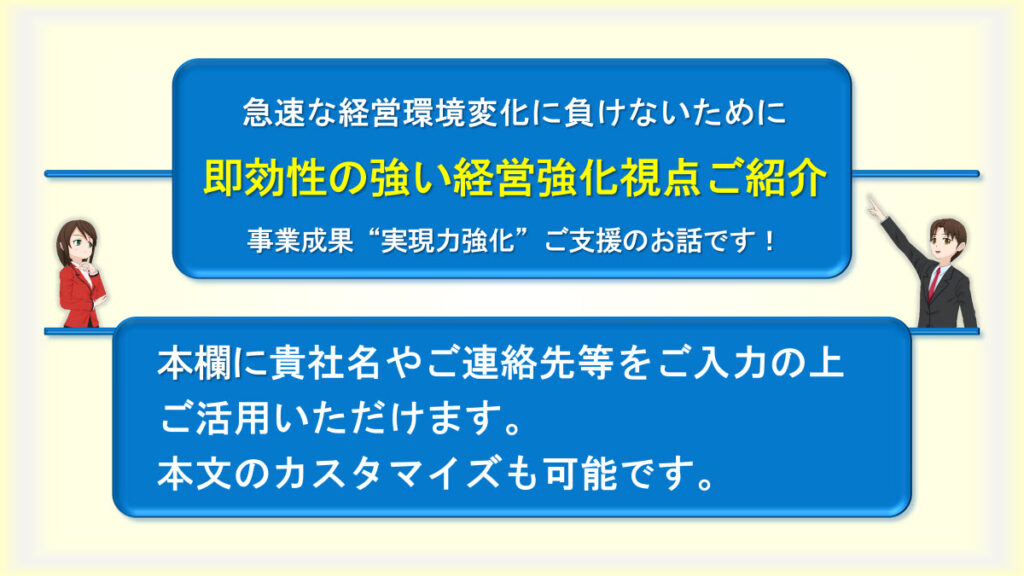経営者との《距離感》は士業ビジネスにとって、これまでも重要かつ微妙なテーマでした。そして《経営者に対して優位な距離感》をとるポジション考察というテーマとなると、一気に難しさが増してしまいます。ところが今、組織で働く現代人の《感性の変化》によって、かつての難題が一気に《解消される機会》が生まれているようなのです。
ご一緒に《確認》しましょう。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.マネジメント理論に無関心だった経営者
マネジメント理論には、一般に《企業戦略》《組織論》《会計学》《ファイナンス》《マーケティング》《生産性:オペレーション》《投資理論》《リスク管理》等、多様なジャンルがあります。ところが、特に中堅中小企業経営者には『そんな勉強は(私には)必要ない』と言われるケースが少なくなかったのではないでしょうか。
それは、中堅中小企業あるいは更に規模の小さい零細企業の経営レベルは《高くない》からなのでしょうか。否、そんな経営者姿勢は、大企業でも同様です。なぜなら、経営学は経営者の本務とは言えないからでしょう。
2.経営者の《本務》とはいったい何なのか?
経営者の本務は、一口に捉えるなら《自社の組織統制》にあります。最近では《ガバナンス》という用語を通じて注目を集め始めた仕事です。ただ、経営者の仕事が《自社統制》にあるのは、多分この世に《組織》が出来て以来《当たり前》のことだったはずです。
そして、多くの経営者は《オーナーとしての立場》や《人柄》あるいは《事業への熟知度》や《先頭を走る主体性》等で、かなり自然に《組織を統制》できていたのです。構成員が自然な形で経営者について行ったということです。
3.組織統制上の無理が少なかった経営者は…
やや《言い方》が不適切になるかも知れませんが、組織統制とは組織内の《専任者=担当者》を自社活動の中に組み込んで《使いこなす》ことに他なりません。指示を与え、その実行を管理し、評価を下すわけです。
そんな統制を比較的容易にできた経営者は、個人差はあっても、同じ姿勢を《社外にも向ける》のです。意識的にであれ、無意識的にであれ、人事労務関連業務の《専門家》をも《一担当者》のごとくに扱いやすいと言うことです。
4.統制者と《業務専任者》との関係ならば…
先生方が、どんなに高度な見識を持っておられても、経営者の意識が『事業の統制者の立場から先生方を捉える』なら、自社の従業員に対するように、『無理を言う』のは当然かも知れません。統制者は『少しでも甘い顔をすれば付け入れられる』ことをよく知っているからです。
それ故、例外は多々あっても、先生方と経営者との関係には《難しい部分》が少なくなかったと、一般的には言えるはずなのです。
5.経営者の《本務遂行》が急に難しくなった
ところが、その《経営者の本務=組織統制》が最近、急に難しくなって来ているのは申し上げるまでもありません。最近、思い出したかのように《ガバナンス=組織統制》が叫ばれているのは、当たり前の統制が難しくなって来ている証拠でしょう。
もちろん、その背景には働き方改革やハラスメント防止法等がありますが、最大の要因は、私たち《現代人》が、経営者の恣意ではなく《合理的》な経営を求めるようになったからだと捉えれます。自己意識が強くなった現代人は、他者に隷属するのを嫌うのです。今までそうだったと知ると、必要以上に隷属を嫌悪します。必要以上に…。
6.合理的な統制=マネジメント手法等の導入
その際、経営者の恣意ではなく合理的な統制が、《ガラス張りのマネジメント》を意味するのは、申し上げるまでもありません。大きな権力を持つ経営者も、権力を背負って仕事をする公務員と同様に、《法やルール》に従って行動して欲しい、と多くの人が願い始めたということです。
そして公務員の《法やルール》こそが、企業経営上の《マネジメント手法》に当たるのです。
マネジメント手法には、人事労務手法のみならず会計学やファイナンス、生産性を上げる業務学やマーケティング、戦略設計や投資回収理論等、様々な分野があり、そこには《専門家》が存在します。これからの経営者は、少なくとも、そうした専門家から《マネジメント遂行上の支援》を得なければ、事業見識や人柄や意欲だけでは、組織を動かせなくなったということです。
7.経営者自身が深くは意識していなくても…
経営者自身が深くは意識していなくても、社内の担当者にも社外の専門家に対しても《向ける目》が変わって来るのは、今や自然なことなのです。そのため、社会保険労務士事務所が緊急に取り組むべき課題が出て来ました。
その課題を端的に捉えるなら、先生方が国家資格者としての《適正手続き》の担い手であるばかりではなく、実際経験の蓄積等から《規程や制度とその適切な運用支援》を通じて、経営者の《組織統制》に役に立つという現実を知らしめることに他なりません。
8.社労士先生方が今、改めて意識すべきこと
その一方で、先生方は《①人事労務問題の解決法》や《②就業規則のみならず様々な規程を必要に応じて提供》し、更には《③評価制度や昇給昇格制度等を必要な範囲内で企画》する社外専門家だと、改めて意識し直すことも重要でしょう。
たとえば『いやあ、人事制度には取り組んでいない』という先生もおられるでしょうが、人事制度という既成概念によるのではなく、『目前の経営者が自社組織の規模に応じて運用できる規程や制度を提供する』と考えるなら、話は違って来るはずなのです。
9.簡便なものでも組織統制に役立つのなら…
たとえば、組織構成員がお互いを熟知できるような規模の組織に《評価制度》を導入する際、《①一定のグループ内で評価のランキングを作成する》、《②そして、そのランキングにした理由を当事者に説明し、今後どうなったらランキングが変わり得るかをも伝える》、《③そのランキングに従って報酬の基本部分を決める》という簡便な方式でも、評価制度になり得ると《考え直してみる》のです。
人事労務の分野では、完璧なものより《組織員が自分たちの理解力によって納得できる》ものの方が大事で、しかも《状況や事情で合理的に変わり得る》と知ることが重要だからです。制度以外の《規程》でも同様です。
10.社会保険労務士事務所のビジネス業務は?
そして、そうした制度や諸規程あるいは、発生したトラブルの解消法等の提案が《スポット契約締結活動》で、その提案の実施が《最初の有料業務(有料)》で、その実施のための社内教育が《初期の研修(有料)》で、その後の継続的な運用サポートが《継続的なコンサルティング契約(有料)》だと捉えるなら、経営者にも先生にも《納得》しやすい経営支援形態を確立しやすくなるのではないでしょうか。
継続的なコンサルティングを《安価なサブスク契約》にし、そこで相談を受けたことを《新たなスポット契約活動》に繋ぐ流れを考えるなら、コンサルティングがビジネスとして成長し始めます。
11.コンサルティングに関しても発想を大転換
更に、古くて新しい課題である《社会保険労務士事務所が担う経営コンサルティング》についても、難しく考え過ぎず、《提供したトラブル防止法や規程や制度の運用の支援や指導》こそが、経営コンサルティングなのだと捉えると、コンサルにまつわる《もやもや》も解消されやすいのではないでしょうか。
経営コンサルティングとは、まさに経営者に対して組織統制を指導支援するものなのですが、契約提案や初期研修は《統制の道具提供》であり、その道具運用こそが《統制支援》だと言えるからです。これは、新たな提案案件のみならず、既に提供している案件についても同様です。今、社会保険労務士事務所の経営コンサルティングのコンセプトも明確化すべき時だと言えそうなのです。