そもそもの始まり

全ての始まりは1990年代に《中堅中小企業経営者向けビジネス&マネジメント・レポートの作成代行》を事業として開発したことから始まります。当初は《金融機関の中堅中小法人市場でのマーケティング支援》でした。
その後、生命保険業界での《中堅中小法人開拓型営業支援》をサービスに加え、更に2002年の士業広告解禁を受けて、《社会保険労務士事務所のと会計事務所のマーケティング支援》に取り組み始めます。
これらの活動の基本は、大企業と中堅中小企業両方の経営コンサルティング経験を生かす形で、《実践的な経営助言を事例レポートを通じて行う》というスタイルでした。
経営事例レポート?
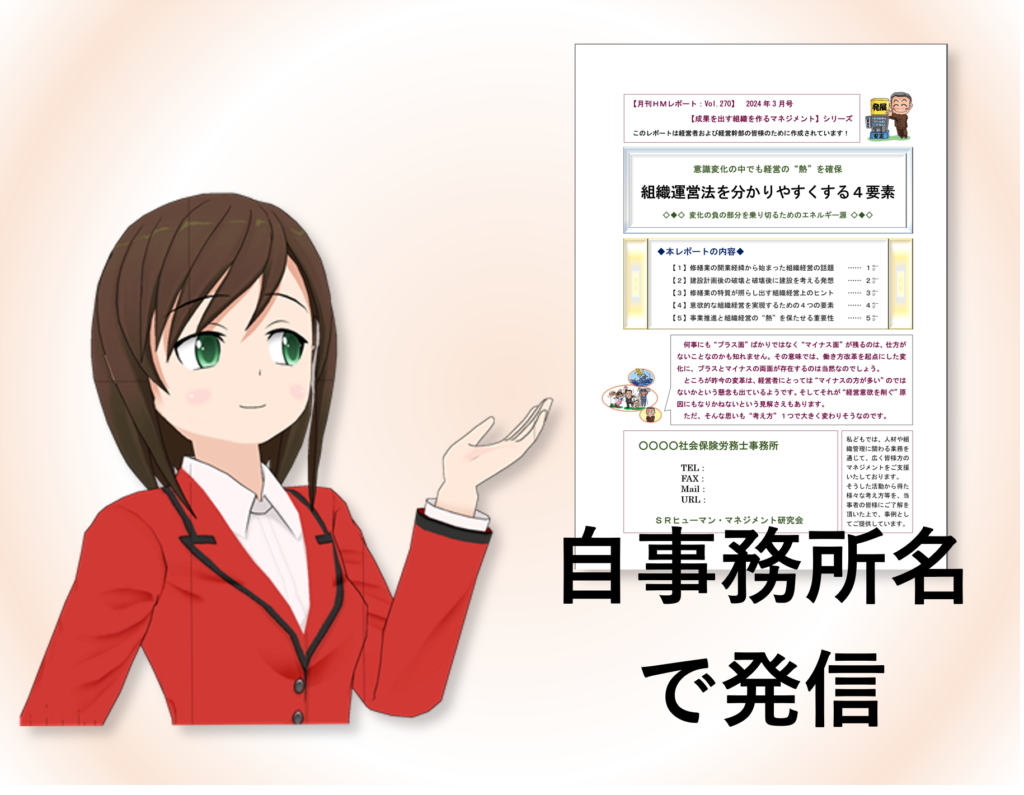
経営の《本姿》は、自社事業上の《問題や可能性》をいち早く見つけ出して、対策や対応の方針を練るところから始まりまります。その《始まり》を支援あるいは動機付けるのが《経営事例レポート》の狙いであり役割なのです。
そのためレポートのは内容は必然的に、具体的な事例とそこから得られる今後の方向性になります。読者となる経営者にとっては、それが『ああ、そんなこともあるな』という程度に終わることも、『それは、わが社のことだ』と痛感することもあるようです。
経営者に気付いて欲しいこと

ただ、ここで重要なのは、《直接的に役立つ情報が多いかどうか》より、現在のような状況の中で、《様々な具体的指摘》を、経営目線で定期的に発信する士業事務所の存在意義を経営者に感じてもらうことなのです。
中堅中小企業の経営者目線の経営情報は、決して多くはないからです。
しかも経営者が、個々の具体的な指摘に動機付けられて、『何とかしよう』とか『行動を起こそう』と思える時に、その内容が、発信者である社会保険労務士事務所の《実践支援》の範囲にあるなら、情報は《単なる勉強事例》に終わるものではなくなります。
先生方サイドでは~1:定期的な働き掛けの確立
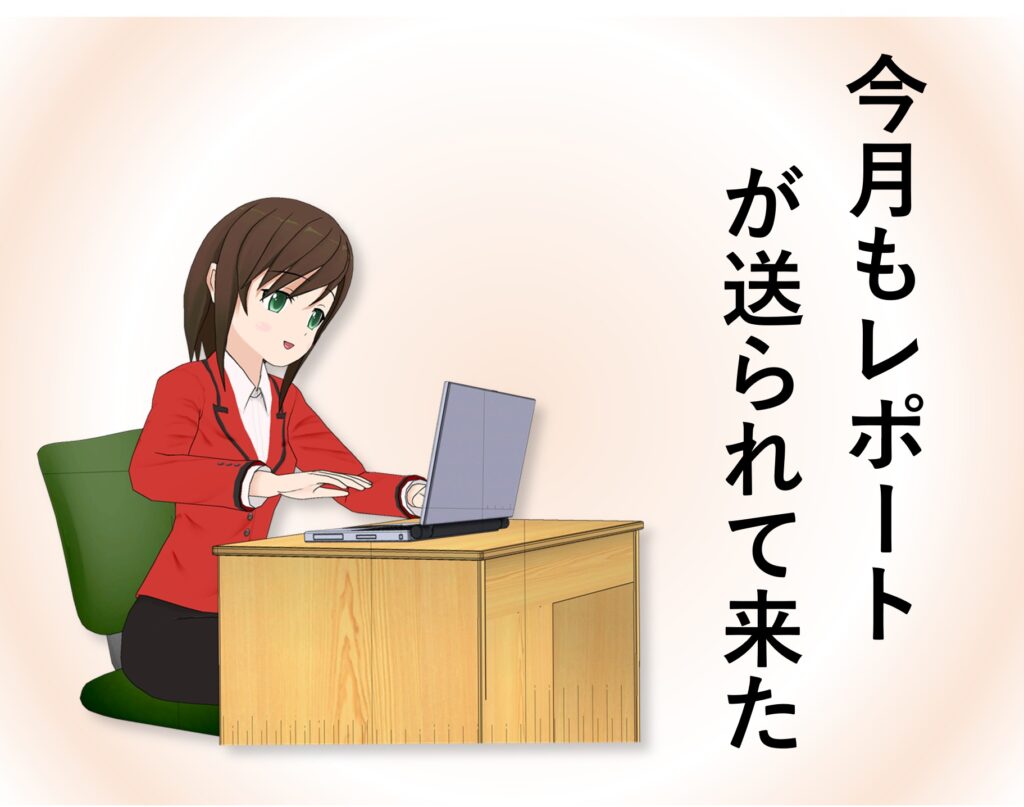
先生方の《専門ビジネス》には、定期的なサービス以外に、不定期に出て来る相談や不都合対策も少なくないはずです。そして、その不定期業務のアンバランスを平準化するために《顧問契約》や《継続的な契約》の形態をとるケースが多いのでしょう。
そんな中で企業側には、『問題等がない月には、専門サービスを十分には受けていない』という不満が残るケースが、案外少なくないのです。
ところが、毎月《マネジメントに関わる重要事例》を提供していると、その《不満》は小さくなり得ます。毎月《何かしら教えてくれる》先生という印象に至りやすいからです。
先生方サイドでは~2:不定期業務の有料化基盤
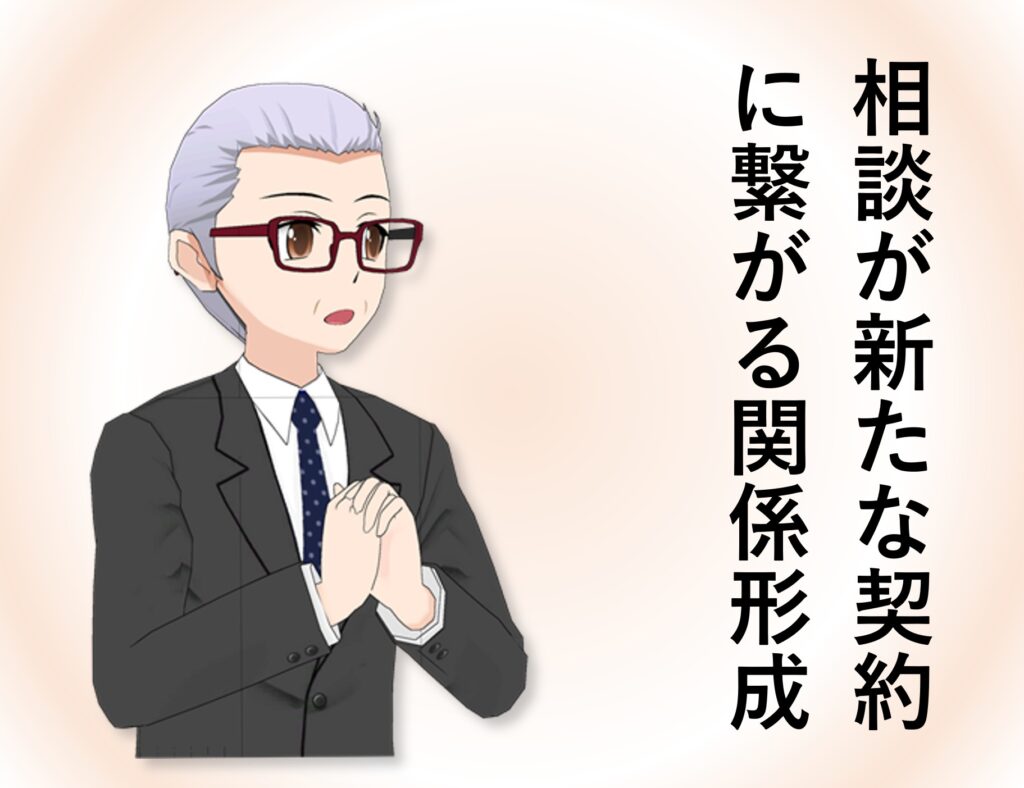
つまり、定期的な提供業務と、定期的な《教育的マネジメントレポート》が合わされば、そこに先生方が受け取る顧問料や業務契約料の《対価》を印象付けやすくなるということです。通常の提供業務以外に何もしないように見える月がなくなるからです。
そのため、新たな相談や問題対応を《定例的な通常業務》とは別にイメージすることが、容易になるのです。
別の《サービス》であるなら、別途有料になる場合があるのは《当然》でしょう。その意味では、月次情報サービスは《業務有料化》の基盤を形成することにもなり得るのです。
先生方サイドでは~3:経営情報の内容形態は?

先生方にご提供する《マネジメント・レポート》は、ほぼ全て《ある経営者の体験や気付き》を例示しています。もちろん《士業らしいまとめ》は行いますが、《1つの個人的体験談》なので、《教える》というより《一緒に考える材料》になりやすいと言えるのです。
更に、対話機会が生じた時のために、詳しい内容解説冊子を付けています。その解説にはレポート内容ばかりではなく、提案やコンサルティング等の方向性まで記します。その目的は、先生方と経営者双方に《ヒント》を提供することにあるからです。
先生方サイドでは~4:新規契約獲得にも効果的
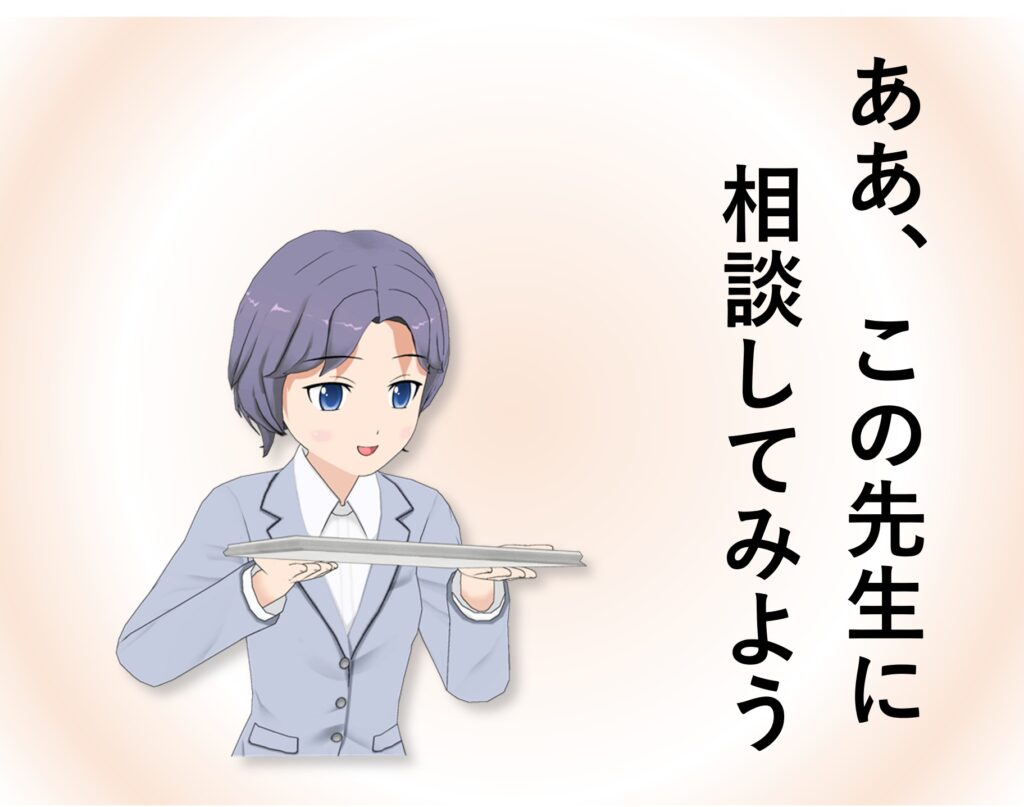
ちょっとした出会いや名刺交換の機会を得た経営者に、マネジメントレポートを提供していると、その中の《話題》を膨らませる形で、顧問契約や継続契約あるいはスポット契約を提案しやすくなるというご報告を、多くの先生方からいただいています。
今後は、労務顧問契約や給与計算代行契約のみならず、ハラスメント回避のための《ルール経営視点》導入、継続的な管理者研修、給与体系見直しから入る賃金規程や昇給昇格制度等、多くの企業に類似の提案ができるスポット契約の重要性も増してくるはずです。
その際には経営者への動機付け要点(話の心臓部)さえ押さえておけば、提案しやすくなるはずです。今人事労務分野は中堅中小企業の《最大課題》になって来ているからです。
社会保険労務士事務所へのご支援の開始と経緯

以上のような見地から、2000年に株式会社エフ・ビー・サイブ研究所を創立した後、2002年3月から本格的に《社会保険労務士事務所が自事務所名で発信可能な経営事例レポートとしてHM(ヒューマン・マネジメント)レポートを提供》する月例情報サービスを開始しました。
更に2004年には株式会社さいぶ編集総研を設立して、《先生のお名前で行う経営セミナーや各種提案のためのツールの企画制作とその解説講座》をお届けする講座とツールのご提供サービスを加えています。
気付きリードマーケティングの会
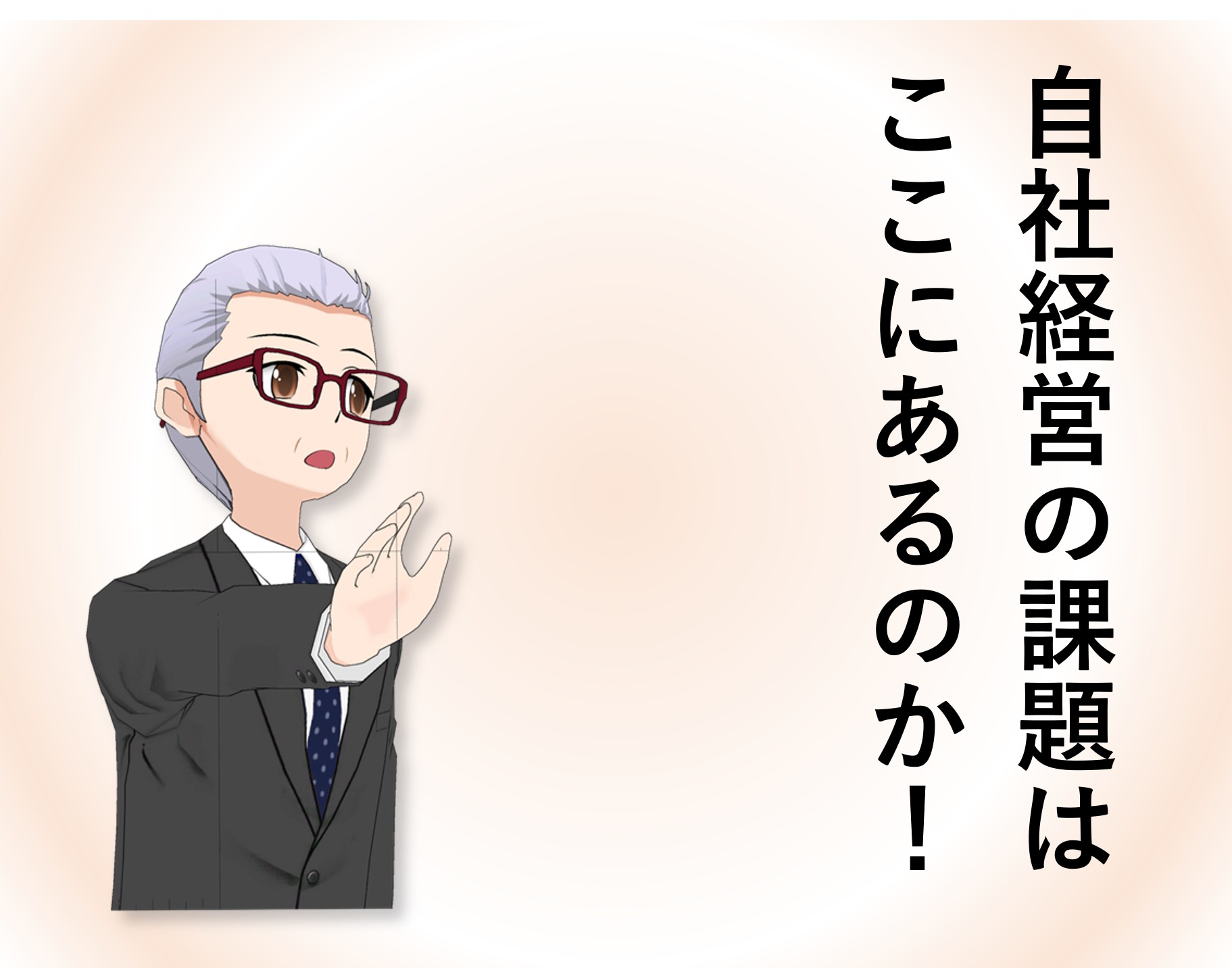
その活動初期の成果は、2008年に《マーケティング》と《有料提案支援》と《セミナー&個別指導支援》の3本柱を基礎にした《気付きリードマーケティングの会》という仕組みに結実いたしました。
これは、先生方のマーケティング支援のために立ち上げた会ですが、《現代情勢下での経営のポイント》がどこにあるかを、事例を通じて経営者に《気付いてもらう》とともに、そのポイント支援者は《誰》であるかを印象付けるための企画でもあるのです。
これからのマネジメント支援の方向性

今後のマネジメント支援には、新しいテーマ導入の前に取り組む重要分野があると言えます。それは、様々な規程や制度の《運用支援》と表現できるものです。そして、それこそが《ルール経営の指導や支援》に他ならないとも言えます。
ただ《コンサルティング=新しい形を提供する》という発想では、この《運用支援》の価値は見えにくいかも知れません。逆に《コンサルティング=うまく実践する支援》だと捉え直すと、大きな《市場》が見え始めるのです。
しかも、その《市場》で先生方が活動するために必要になるのは、《社会保険労務士事務所の日常的業務を有料化する技術》と《提案力》を磨くことだけかも知れません。
今後の展開は?
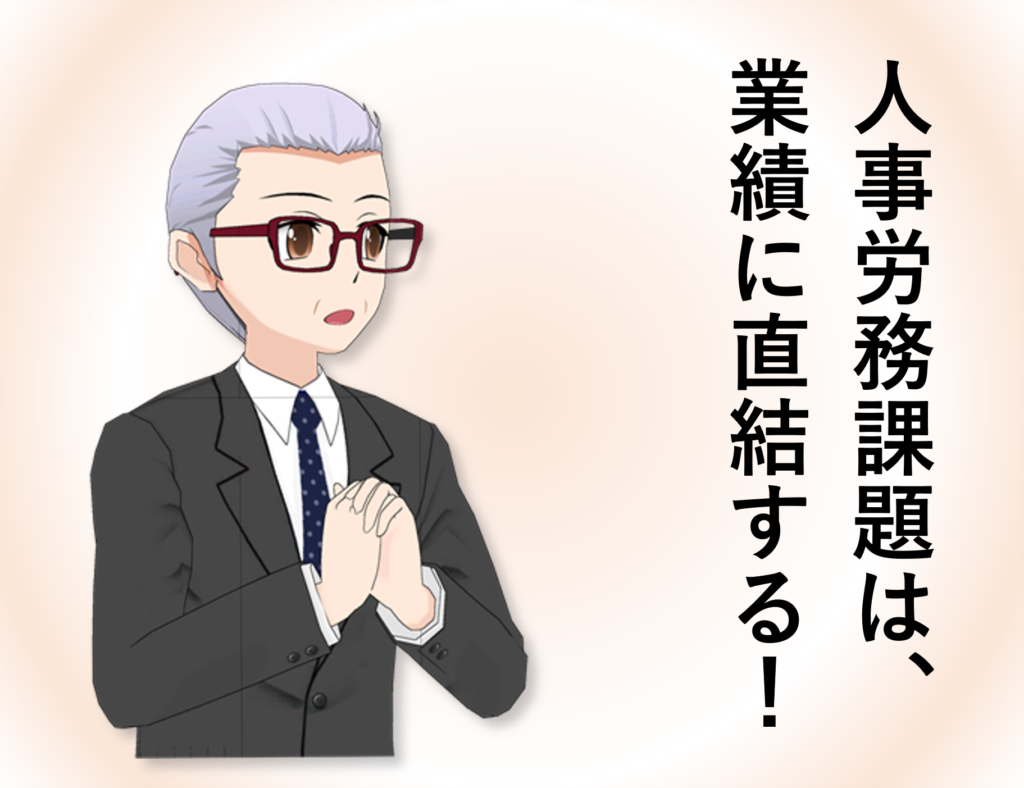
事業環境のみならず社内環境(人員問題)に苦しまざるを得ない中堅中小企業では、今後益々組織マネジメント(人事労務課題)の支援者なしには、事業継続のための業績力を確保できなくなりそうです。先生方の存在は、益々重要になるのです。
ただし、経営者の実感を更に深めるには、人事労務課題への取り組みが、今後は一層業績に直結するという《経営意識》が重要になります。
《気付きリードマーケティングの会》は、そうした《経営者の意識高揚》のお手伝いに、今後も取り組んで参ります。
企業経営支援者の皆様の支援者として

そうした《経営支援者としての先生方》の支援者として、情報発信支援の他に《ホームページの制作及び運営》や《メルマガ作成代行》、《ご要望に応じた経営者向けセミナーや社内研修の作成》や提案書やDMや業務内容説明のための《ツール作成》、あるいは《先生方の業務生産性の向上支援》等のご依頼に関しても、広く取り組んでまいりたいと考えています。
今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
